観測史上最高となった今夏の平均気温をはじめ、いまや酷暑が当たり前になっている。その結果、今年も昨年以上にコメ不足が起こるのではと懸念されている。こうした状況の中で、救世主と期待されているのがビール酵母だ。ビールとコメ、なんとも意外な組み合わせだが、ビールづくりで使用された副産物であるビール酵母、さらにいえばその酵母細胞壁から生みだされた農業資材が、稲作農家をはじめとする農業界で大きな注目を集めているのだ。資材を開発したアサヒバイオサイクルを訪ね、社長の千林紀子氏に話を聞いた。
生物本来の力を引き出す「バイオスティミュラント」
「ビール酵母細胞壁を農業分野に展開しはじめたのは2017年と最近ですが、ビール酵母自体は100年近く活用されています」と、千林氏が言うとおり、昭和5年発売の「エビオス錠」(アサヒグループ食品)があるなど、酵母活用の歴史は長い。また、酵母から抽出したエキスは食品の調味料に、殻の部分にあたる細胞壁も食物繊維が豊富であることから、これまで飼料に使われるなど、ビールをつくった後も大活躍の微生物だった。それが、さらに農業分野にまで進出するきっかけとなったのは、研究者が2017年に立ち上げた社内ベンチャーが、細胞壁に独自の水熱反応技術を施すことで植物の成長を促すことに成功したからだ。
この特許技術は、従来の化学系の農薬や農業資材と違い、食品由来の資材として環境負荷が少なく、また、植物の持っている能力を引き出すバイオスティミュラント資材として高い評価を受けている。高い評価は、効果以外にもある。それが世界でも有数の肥料原料や農薬原料供給国であるロシアとウクライナの紛争によって農薬などの価格が急騰し、農家経営を圧迫していたからだ。バイオスティミュラントが国内で製造できれば食料安保にもつながり、環境負荷の軽減にも貢献できると、政府が推進する農業政策である「みどりの食料システム戦略」でも期待の高さがうかがえる。
そして、実際に効果を発揮しているのが、猛暑によって不作が心配される稲作の現場。
「水田に手を入れるとわかるのですが、お湯なんですよ。根を抜くと茶色に変色しており、このままだとコメ自体も茶色くなりますし、収量も減ってしまいます。一方、節水型乾田直播(かんでんちょくは)栽培であれば、炎天下でも根元は涼しく、水のせいで余計に熱くなることもない」と千林氏はいう。
節水型乾田直播とは、聞きなれない言葉かもしれないが、漢字からわかる通り「乾田」は、水を張らずに稲をつくるやり方で、「直播」は、苗を育て田植えをするのでなく、直接、種を播くこと。もちろん、水をまったくやらないわけではないが、水田での栽培に比べれば大幅に少なくて済むので節水型というわけだ。おまけに、水を張らないのでメタンガスの発生も抑えられる。
そして、この直播の際にアサヒバイオサイクル社のビール酵母資材を使うことで、種の発芽を早め、成長を促して、収量を維持できるという。
稲作に使われる前もゴルフ場や競技場で芝生を養生し、北海道の余市町にある「ニッカ余市ヴィンヤード」などでも、日本ワインづくりに効果を発揮してきたが、稲作に関わりはじめたことで需要が高まっている。では、いかに稲作と関わるようになったのか。そのきっかけは、北海道の農家からの相談だった。
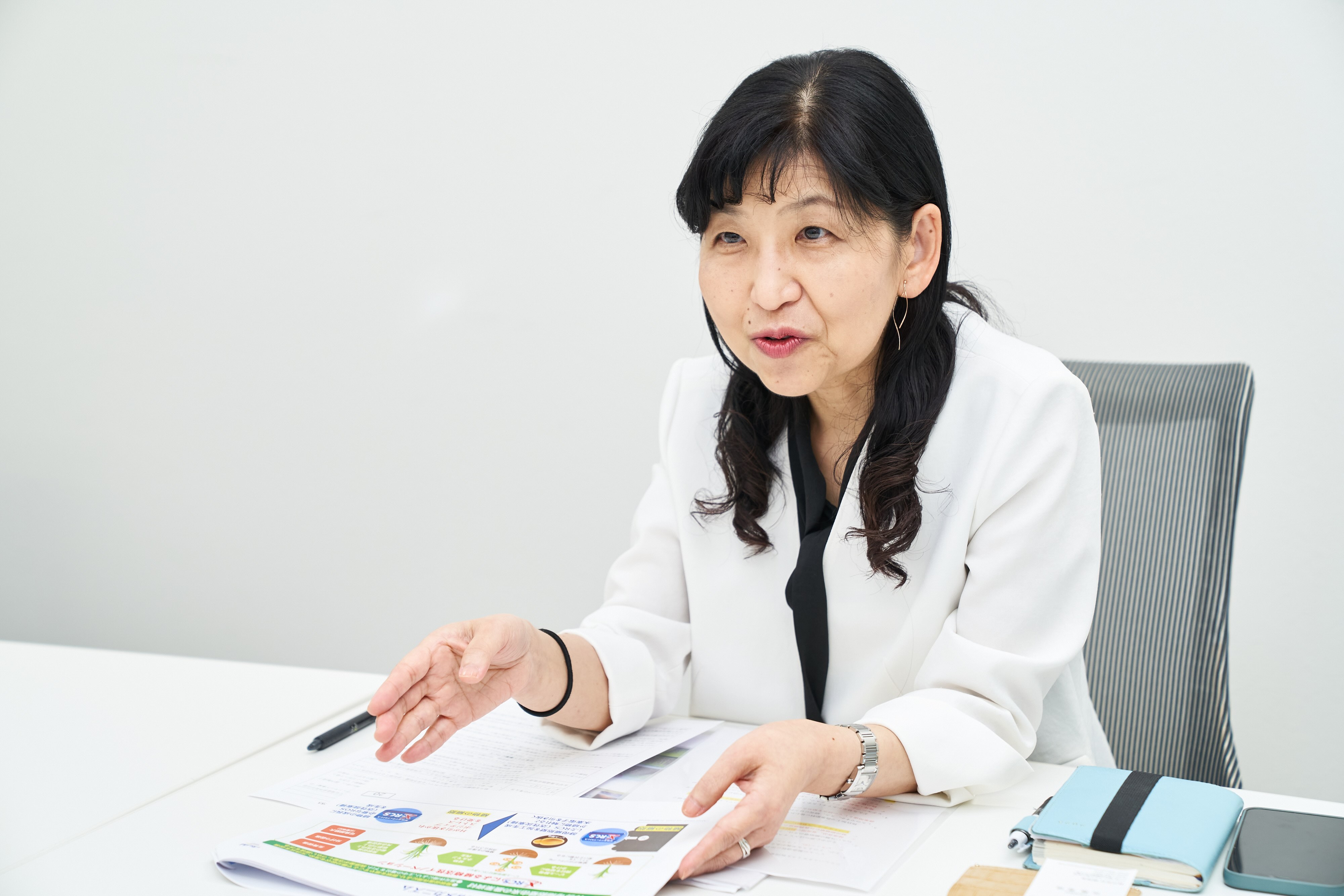
“乾田”で美味しいコメはできるのか?
「網走にある福田農場さんは、2018年から畑で稲を育てる陸稲の栽培をはじめたのですが、1年目、2年目と良い結果が出ませんでした。当社のバイオスティミュラント資材をジャガイモなどにも使用していただいていたことから、コメにも資材を使ってみたところ、翌年、待望の成果を手にしたのです。いまは増産し、周囲の農家さんたちまで稲作を始めています」と千林氏。この成功体験が、酷暑に苦慮する稲作農家に節水型乾田直播など「水を張らない」選択肢を提案していくきっかけになったという。
ただ、先人から受け継いだコメづくりの常識があることから、農家の反応も慎重で、「実際にトライしていただいている方たちも最初は10%だけ、翌年は30%と様子をみながら乾田直播の圃場を増やしている状況です。とはいえ、水の管理を殆どしなくていいので生産性は上がり、田植えがないので苗をつくるハウスなどの設備投資を必要としないことから、ずいぶん作業がラクになったとおっしゃってくださっています」と、千林氏は手ごたえを口にする。
ただ、問題は味。どんなに生産性が上がろうが、コストが下がろうが、美味しくなければ広まらない。その点を聞いてみると、「農家さんでも『陸稲は美味しくないでしょう』と言われる方がいますが、技術の進歩で、いまや味は変わりません。等級もこれまでの作り方と変わらぬ結果が出ています。もちろん、じっくり時間かけてつくるスーパープレミアムなおコメであれば、水田の良さは絶対にあると思うので、ケースバイケースで、いろんな選択肢がありますよという状況を作っていければいいと思っています。でも、福田農場さんが陸稲で作る「ななつぼし」は、本当に美味しいですよ」と、味にも太鼓判を押す。
千林氏たちが、節水型乾田直播や陸稲といった水を張らないコメづくりを広めていきたい理由は他にもある。それが農家の労働生産性の問題だ。

労働生産性問題は稲作にも
先進国で最低など、生産性はどの業界でも最大の課題と言われ続けているが、農業も例外ではない。統計でも、米国や豪州、アジアとの比較で生産性が低いのがアジアと日本だが、今やアジアからも抜かれようとしており、投下労働時間を見ても日本は断トツに高い。
農家の規模が大きい米国や豪州に比べれば、どうしても不利にはなるが、水田での稲作もまた大きな要因になっている。実際、米豪の田んぼは水を張って直播きする湛水直播が一番多く、次いで乾田直播、水田、陸稲と続くが、アジアと日本は圧倒的に水田が多く、日本に至っては9割近くが水田だ。稲の種類や味も変わらないのであれば、水田が酷暑による影響を一番受けるので、乾田での栽培に変えて、70日ほどかかる水管理を5日ほどに減らし、直播にすることで代かき、苗づくり、田植えが必要なくなることもあるので、検討しても良いだろう。
千林氏もすべてを変えるつもりはなく、バランスが問題だという。「プレミアムなお米づくりをするために水田はまだまだ必要ですし、棚田などの景観の問題もあります。例えば、今年は酷暑だから節水型乾田直播のウェイトを高めにし、気候が安定していればプレミアムなコメづくりをするために水田も導入するなど、稲作の選択肢の知見を蓄積してフレキシブルな対応ができればいいのではないかなと思っています。それがコメ不足にも対応でき、生産性もあがる最適なやり方だと信じています」。

その想いは、海を越えて広がる。現在、アフリカでも稲作が行われているが、人口増加で生産が追い付かず、干ばつの問題もあるため輸入に頼っている。ところが、一昨年、最大の輸出元であるインドが干ばつで輸出ができなくなり、最大の輸入先であるアフリカでは食料安全保障に対する取り組みが活発化した。アサヒバイオサイクル社もケニアで節水型乾田直播の稲作を支援しており、「今年7月にはじめて収穫しましたがバイオスティミュラントの効果で84%も収量が増えたと報告がありました。まだ、一期目なので再現性の試験が必要ですが、アフリカでも食の問題を解決したいと考えています」。一方、国内の目標はと訊ねると、「日本のコメを輸出できるビジネスにしていけたら嬉しい」と千林氏。そうなると酵母が足りなくなりそうだが、「アサヒグループには世界中にビール工場があるので、まだまだ大丈夫」と笑った。

