排他的経済水域はいたてきけいざいすいいき EEZ
境界線の根拠を主張して多くの国が対立
海に面した国に対して、水産資源や海底鉱物資源などに関する経済的な権利が認められている水域。1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、1994年11月16日に発効した、海の憲法とも呼ばれる「国連海洋法条約(海洋法に関する国際連合条約)によって新たに創設された。
沿岸から200海里(約370キロ)までの範囲が排他的経済水域(EEZ)にあたり、沿岸から24海里は「接続水域」、沿岸から12海里は「領海」とされている。EEZ域内の資源に関しては経済的権利を優先できる。「領海」とは異なり、外国船舶も公海上と同じように自由に航行が可能で、沿岸国の同意を得れば科学目的の調査も実施できる。
EEZが複数の国で重なる場合、国連海洋法条約によると、当事国同士の交渉で境界を画定することになっている。しかし、経済的な資源の開発権利を含む問題だけに、それぞれの国が異なる境界線の根拠を主張して対立する場合も珍しくない。日本も韓国、中国、台湾、ロシアと境界の画定で対立している。
海に囲まれた島国日本は、EEZの境界画定で譲れない
日本は海に囲まれた島国だから、EEZの問題にはナーバスになるよね。日本のEEZ面積は447万平方キロメートルもあって、国土面積38万平方キロメートルの約12倍。領海も含めた排他的経済水域の面積は、世界6位。
昔は漁業権ぐらいの話だったが、近年はメタンハイドレートやレアメタル、レアアースなどの資源が見つかり、しかも掘削技術が発展したことで、日本海溝やマリアナ海溝でも資源を掘り起こせるようになり、EEZはますます重要性を増してきている。
そんなわけで、日本もEEZの問題には力を入れている。東京から1700キロほど南にある沖ノ鳥島では、島の周囲をコンクリートやブロックで固め浸食を防いでいる。沖ノ鳥島が沈んだら日本のEEZは大きく減るから。
中国と韓国はそんな日本の行動を非難して、沖ノ鳥島はEEZの起点には成り得ないと主張しているけど、2012年4月に国連が沖ノ鳥島を条約上の「島」であることを認定した。
沿岸から200海里だから、EEZが他国と重なることはよくある。当事者国の話し合いで解決することになっているけど、話し合いで簡単に決着する問題じゃない。お互いに引く理由がないもの。だから、国境紛争と同じでなかなか解決しない。


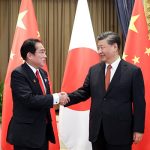









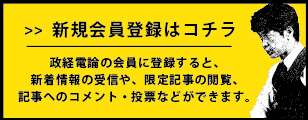
ん
あ
2024.5.28 09:56
オーストラリア
問題多い
2024.1.18 23:01
ヤスヒロ
近年、何度となく中国が日本のEEZ水域で、勝手に海洋調査をしてますが、これについて、皆さんはどう思われてますか?
私は、人の庭を勝手に調査されているように思いますが、いかがでしょうか?
政府として、毅然とした態度がもとめられますね。 先般、石垣島の漁師さんが、魚を撮りに出られないと…,。嘆いていました…。
2023.10.24 08:43
匿名
あ
2023.7.20 10:09
匿名
それなー
2023.6.5 20:42